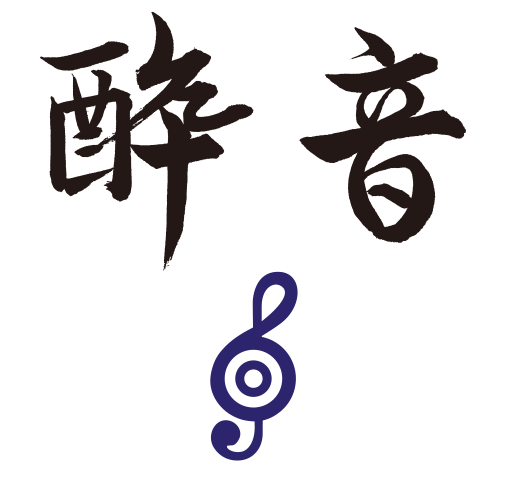終電まではまだ少し時間がある。定例会からの解放感もあり、少しその辺をうろついてから帰ろうかと考えた。
大久保通りから路地裏に入り、狭く薄暗い細い道を歩く。住宅街に混じって、営業しているのかしていないのか分からない商店が数軒。周りに人がいないのを確認してから、煙草に火をつける。
煙を吸い込み、吐き出す。辺りを少し散歩してから、終電の三十分前には帰ろう。そう考えながら、車一台通れるほどのこの狭い道に向こうからワンボックスの車が入ってくるのをぼんやりと眺めていた。ワンボックスの車が通り過ぎるかと思いきや、突然目の前で止まった。
後部座席のドアが開き、男が飛び出してきた。男の手が俺の肩を捕まえ、力任せに車の中に押し込んでくる。勢いを止められず座席の上に転がり込むと、中にいた別の男が割れた日本酒の瓶を突きつけてきた。
「騒ぐな。静かにしねえと殺すぞ」
俺を車内に押し込んだ男も車に乗り込んできて、二人に挟まれる形になる。状況が理解できず、とにかく何度も何度も頷き、割れた瓶を持った男の言うとおりにした。
車が何処かへ向かって走っている。後部座席に俺を含めた三人、運転手が一人。混乱していたせいでどれくらいの時間走っていたのか全く分からない。言葉を発する事もできず、ただひたすら恐怖に耐えていた。
何処かの敷地内に入るような、砂利の上を通る音。何が起きているのか全く分からなかった。車が止まり、外に連れ出された。
町工場のような場所。後ろから日本酒の瓶を突きつけられたまま室内へと入る。完全に堅気ではないであろう、見るからに危なそうなこの男達とトラブルを起こした記憶などない。間違いなく誰かと間違われている。勘違いで殺されてしまうなど御免だ。絶対に誤解を解かなければいけない。
町工場の中に、俺を拉致した連中と同じような雰囲気の男が二人立っていた。リーダーのような雰囲気の男が俺の顔を睨め回し、他の男たちに向けて怒鳴った。
「てめえら、しくじりやがったな。こいつは小倉じゃねえ。誰だこいつは」
「すいません、ライブハウスから出てきたのでてっきり」
「この馬鹿野郎。長谷川、てめえ、後で事務所戻ったらヤキ入れてやるから覚悟しとけよ」
小倉。通称・ビート。俺が拉致された原因はあいつだった。ビートが何かをやらかした。男たちはビートを拉致しようとして、間違えて俺を攫った。そういえば、ライブハウスで殺っただの殺らないだの言っていたのはそういう事だったのだろう。
男が俺の方を向いた。優しさの欠片もなさそうな冷たい目だった。
「おい。誰だよ、おめえ」
「加藤健太郎です」
「名前なんて聞いてねえんだ馬鹿が。ライブハウスから出てきたんだろ、小倉の身内か?」
身内か、と言われたら違うとも言えない。血縁関係の話ではなく、イベント関係での話だ。友人であるし、イベントに関して言えば身内としか言いようがなかったので、仕方なく頷いた。
「小倉のイベントで、VJをやっています」
声が震えるのを抑えながら何とか喋ると、男が舌打ちをした。
「VJだってよ。てめえらVJ連れてきてどうするんだ。全くどうしようもねえ。おい長谷川、もう一度ライブハウス張ってこい。いなきゃ周囲の店を探せ。見つかりませんでした、じゃ済まさねえからな」
ビートの野郎、一体何をしたのか。こんな連中を敵に回してどうするつもりなのだ。完全にやくざ映画の世界だ。
この件は後でビートにたっぷり文句を言って、どさくさに紛れてそのままイベントも引退させてもらわねばならない。俺は反社会勢力の一員になった覚えはない。
「このVJはどうします」
「殺して神田川にでも放り込んどけ、明日の朝刊に間に合うように、目立つようにな」
命令された男が頷き、巨大な日本酒の瓶を持って近づいてくる。予想外だった。いくらなんでも命までは取られないだろう、と考えていたのは甘かったようだ。冗談を言っている雰囲気は男達にはない。
「勘弁して下さい、死にたくない、俺はそもそも、嫌々イベントに参加していたんです。断っても拒否されて、あの、何があったとか知らないし、俺は関係ないんです」
命乞いをする俺に、リーダー格の男が笑いながら蹴りを入れてくる。大した衝撃ではなかったが、恐怖で身体が固まっていて抵抗できず、そのまま地面に倒れ込んだ。
「兄ちゃんよ、関係ないって言ってもな。『そうだったんですか関係ないならどうぞお帰り下さい』なんてのが通用する世界じゃねえってことはおめえもDJイベントの世界にいるなら分かるだろ。腹括れや」
そんな馬鹿な。言っている事がまるで滅茶苦茶だ。やくざのようだが、この連中もどうやらDJらしい。日本のクラブシーンはいつからこんな事になったのだ。馬鹿げている。クラブで曲を流すのがDJだ。クラブで映像を出すのがVJだ。クラブでのイベントを企画するのがオーガナイザーだ。決してこんな、やくざの様に命のやり取りをする事ではなかったはずだ。
突然、携帯電話の着信音が鳴った。リーダー格の男のポケットから鳴っていた。男が携帯電話を取り出し、面倒臭そうに通話ボタンを押して話し始める。
何とかこの場を切り抜けなければならない。切り抜ける事が出来なければ、待っているのは死だ。理不尽な死。俺はただ、仲間とDJイベントに参加していただけだ。こんな馬鹿な話があるか。
「誰だてめえ、何で俺の番号知ってんだ」
電話をしている男の顔つきが変わっていく。電話の相手は誰なのかは分からない。
「教えたのは長谷川か、裏切りやがったな。てめえ、小倉だな」
電話の相手。ビート。何がどうなっているのか状況が全く分からないが、この電話が奴からの助けであることを祈る他なかった。
暫くして、男が電話を切り、ゆっくりとこちらを睨みつけてきた。怒りに満ちた表情だった。
「大したもんだ、お前んとこのオーガナイザー、こっちの動き全部把握してたってな。VJは好きにしろってよ。見捨てられたな」
男が、子分の持っている巨大な一升瓶を奪い取った。ビートからの電話。救いにはならなかった。救いどころか、完全な死の宣告だった。
「待ってくれ、本当に俺は何にも知らないし関わってもいないんだ。俺はただイベントで映像を出していただけだ」
「もう諦めろ。ああ、殺す前に、小倉から伝言だ。小倉からだが、内容はシゲムラって奴のメッセージだから伝えてくれって、よく分からねえ事を言ってたな。『つみれともずく超かわいい』だってよ。何のこっちゃ?」
「あのクソ野郎!!」
怒鳴り、絶叫した。それが合図かのように男が頭上に一升瓶を振りかざした。怒りと死への恐怖で目が霞む。俺はハメられたのだ。同い年の友人二人に。
誰がいつ言ったのか覚えていないが、イベントのメンバーの誰かから『五十六年生まれの人間は皆ろくでもない』と言われたのをはっきり覚えている。その通りだ。
男が一升瓶を振り下ろした。意識が消えていった。